- ホーム
- 不動産の相続で覚えておくべき基礎知識 ~手続き・書類・諸費用~
inheritance
不動産相続の手続きをスムーズに進めるために押さえるべきこと
不動産相続は、権利関係など考えることが多く手続きも煩雑なため、何から手をつけるべきか不安に思われる方もいるでしょう。突然の不動産相続で慌てないように、基礎知識を押さえておくことが大切です。ここでは、名古屋市を中心に不動産相続をサポートする悠久ホームサービスが、不動産相続の手続きや書類、諸費用などの基礎知識を紹介します。不動産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
不動産相続でお悩みはありませんか?
- 不動産相続の手続きが分からない
- 不動産相続にかかる費用が心配
- 不動産を相続したが遠方に住んでいるため管理が難しい
- 不動産を相続したが住む予定がないので売却したい
- 不動産を相続したが共有となり話がまとまらず困っている
- そもそも不動産相続で何をしたら良いか分からない
不動産相続の種類
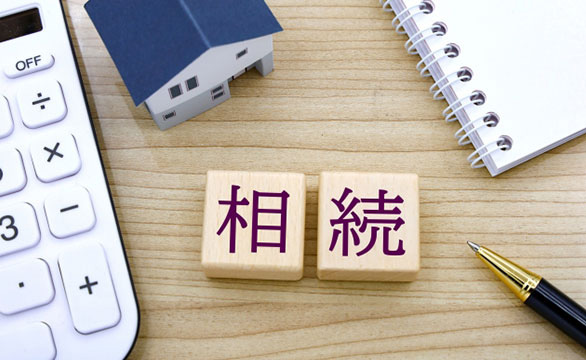
不動産相続には、主に「遺言による相続」「法定相続」「分割協議による相続」の3つがあります。それぞれの違いや手続きについて、分かりやすく解説します。不動産相続の仕組みを知り、トラブルを未然に防ぎましょう。
遺言による相続
遺言による相続とは、遺言書がある場合にその内容に基づいて遺産を相続する方法です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や要件が異なります。遺言相続では、法定相続に優先して遺言書の内容が有効となります。
しかし、遺言によって法定相続人の取り分が大幅に減らされる場合、一定の範囲内で最低限の財産を請求できる権利(遺留分)があります。遺留分を持つ相続人は以下の通りです。
- 配偶者
- 子ども、代襲相続人(直系卑属)
- 両親、祖父母(直系尊属)
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使できます。
また遺留分の割合は、民法により次のように定められています。
- 直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1
- それ以外の場合は相続財産の2分の1
法定相続
法定相続とは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残さずに亡くなった場合に適用される方法です。民法で定められた相続順位や相続分に従って遺産を分割していきます。配偶者は常に相続人となります。
第1順位 子・その代襲相続人(直系卑属)
第2順位 父母・祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹・その他代襲相続人(傍系血族)
の順となります。
それぞれの相続分についても民法で定められています。
| 法定相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:1/1 |
| 配偶者、子 | 配偶者:1/2 子(全員で):1/2 |
| 配偶者、父母 | 配偶者:2/3 父母(全員で):1/3 |
| 配偶者、兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹(全員で):1/4 |
例えば、配偶者と子2人が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が4分の1ずつを相続します。
分割協議による相続
遺言がない場合や、遺言に財産の分け方が指定されていない場合、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により財産を分ける方法です。相続人全員の合意が必要で、遺産分割協議書を作成することで、正式に合意内容が確定します。
不動産の相続手続き(相続登記)の流れ

不動産を相続した際に、家や土地の名義を変更することを「相続登記」といいます。相続登記は、令和6年4月に義務化されました。不動産を相続する際は、相続人を決定した上で、所有者の名義変更をしましょう。ここでは相続登記の申請の流れを解説します。
1.不動産を相続する人の確定
あらゆる相続において最初にやるべきことは、相続人の確定です。そのため、まずは公証役場の「公正証書遺言の検索システム」を活用して、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がない場合、または遺言書の内容に異議がある相続人がいる場合は、遺産分割協議を行います。法定相続人全員で協議し、不動産の相続人や分割方法、割合を決定します。遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の署名・押印がある「遺産分割協議書」を作成してください。
2.相続登記の手続きに必要な書類を集める
相続登記の手続きには、不動産に関する以下の書類が必要です。また、遺言書による相続と、遺産分割協議による相続の場合は、それぞれ追加の書類を集めなければなりません。
法定相続による相続の場合
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍を含む) | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 取得者の住所地の市区町村役場 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 |
| 登記申請書 | 法務局のホームページからダウンロードまたは自作 |
遺言書による相続の場合
法定相続による相続の場合に必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれか) | 自筆証書遺言:自宅等 公正証書遺言:公証役場 秘密証書遺言:自宅等 |
遺産分割協議による相続の場合
法定相続による相続の場合に必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
3.登記申請書の作成
必要書類が揃ったら法務局で相続登記を申請します。このときに必要な「登記申請書」は自身での作成が可能です。登記申請書の雛形は法務局のホームページより入手できます。記載例も掲載されているため、確認しながら登記申請書を作成しましょう。
不動産相続にかかる諸費用
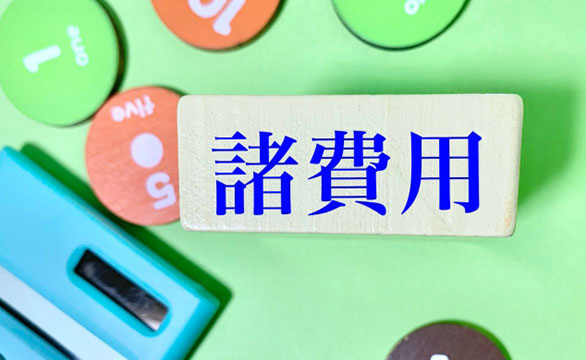
家や土地などの不動産を相続する場合、税金や手数料、書類取得費用などの諸費用が発生します。ここでは相続税をはじめとした税金や諸費用について詳しく紹介します。
相続税
相続不動産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を上回る場合、基礎控除額を超えた分に相続税が発生します。土地の相続税評価額は国税庁のホームページに掲載されている「路線価」、建物の評価額は、市区町村が発行する「固定資産税課税明細書」または「固定資産評価証明書」で確認できます。
また、一定の条件を満たす場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった控除が適用され、相続税の負担を軽減できます。小規模宅地等の特例では、被相続人の居住用宅地等の評価額を最大80%減額できます。配偶者の税額軽減では、配偶者が取得する財産について、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税が課税されません。
固定資産税・都市計画税
不動産を相続すると、その所有者には固定資産税と都市計画税の納税義務が生じます。これらは地方税であり、不動産の所在する自治体ごとに税率や計算方法が異なります。これらの税は、毎年1月1日時点の所有者に課せられ、自治体から4月~6月頃を目安に納税通知書が送付されます。
詳しい税率や計算方法については、不動産が所在する自治体のホームページをご確認ください。
登録免許税
相続登記の際には、登録免許税が発生します。登録免許税の税率は、固定資産税評価額×0.4%です。なお、相続人以外が遺言によって不動産を取得した場合の税率は2%です。また、相続する土地の評価額が100万円以下の場合は登録免許税が免除されます(建物は対象外)。
譲渡所得税
不動産を売却して利益が発生した場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。税率は、不動産の所有期間によって異なり、取得から5年以内の短期譲渡所得では39.63%、5年以上の長期譲渡所得では20.315%となります。また、土地の購入費用や建築費用などは「取得費」として計上でき、売却収入から差し引くことが可能です。
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 所有期間 | 区分 | 税率(所得税+復興特別所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63%(30%+0.63%+9%) |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315%(15%+0.315%+5%) |
| 10年超(居住用財産) | 10年超所有軽減税率の特例 課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分 |
14.21%(10%+0.21%+4%) |
| 10年超(居住用財産) | 10年超所有軽減税率の特例 課税長期譲渡所得6,000万円超の部分 |
20.315%(15%+0.315%+5%) |
必要書類の取得費用
上記で紹介したように、相続登記には多くの書類が必要です。中には取得費がかかる書類もあるため、事前に把握しておきましょう。具体的な書類と取得費は以下の通りです。
- 登記事項証明書:不動産1件につき600円
- 戸籍謄本:1通450円前後
- 印鑑登録証明書:300円前後
司法書士・税理士への依頼料
相続手続きを司法書士・税理士に依頼する場合は依頼料がかかります。依頼先により費用は異なりますが、目安としては以下の通りです。
- 司法書士への依頼料:50万円前後
- 税理士への依頼料:相続財産の0.5%~1%前後
