- ホーム
- 相続人にできる対策とは
subject
相続人側の対策で円滑な不動産相続を目指そう!
相続は、ある日突然発生する可能性があります。相続の発生を知ったら、相続人は名義変更や相続税の申告などを行わなければなりません。突然の相続によるトラブルを防ぐためには、あらかじめ相続人側でも対策することが大切です。ここでは、愛知県名古屋市にある悠久ホームサービスが、不動産相続前にできる対策と、相続後に行う手続きについて紹介します。
不動産相続前に準備しておくべき手続きと節税対策

不動産相続では、金銭面や権利関係などさまざまなトラブルが発生しがちです。これらの相続トラブルは、事前に対策することである程度防げます。主に「任意後見制度」の活用と「相続税対策」を行うことで円滑な不動産相続を実現できるでしょう。
任意後見制度とは
任意後見制度は、被相続人が十分な判断能力を持っているときに、あらかじめ信頼できる相続人を任意後見人に選任し、不動産取引などの権利を委任する制度です。例えば、被相続人が認知症などで判断能力を失った場合、相続人単独では不動産の売却などの手続きができなくなります。こうした場合も、事前に任意後見人を選任することで、相続人が被相続人に代わって不動産を売却することが可能です。これにより、「実家を売却して介護施設への入居費用や医療費を捻出する」という選択もできます。
任意後見契約は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所を通じて行い、公証人が作成する公正証書によって締結します。契約にかかる費用は、公正証書作成の基本手数料(11,000円)、登記嘱託手数料(1,400円)、印紙代(2,600円)などがあります。また、士業(司法書士・弁護士)に依頼する場合は、手数料を含め15万円前後かかることが一般的です。
相続税の対策
相続税は、被相続人から相続または遺贈により取得した財産の合計額が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合に、その超過分に対して課税されます。こうした相続税も、事前に対策することで節税できます。特に効果的な対策となるのは、次の3つです。
- 生命保険の非課税枠を活用する
- 贈与税の非課税枠を活用した生前贈与
- 土地の相続税評価額を引き下げる
被相続人が生命保険を活用していた場合、生前の財産から生命保険の掛け金を拠出することで、将来の相続財産を減らすことができます。支給される生命保険金には一定の非課税枠を適用できるので、相続税の負担を軽減可能です。
また、被相続人から贈与税非課税の範囲内で生前贈与を受けることで、相続時の財産が少なくなり、相続税額を節約できます。所有している土地にアパートを建てるなど土地の相続税評価額を下げる手段も節税に効果的です。
不動産相続後に必要な名義変更と相続税の申告方法
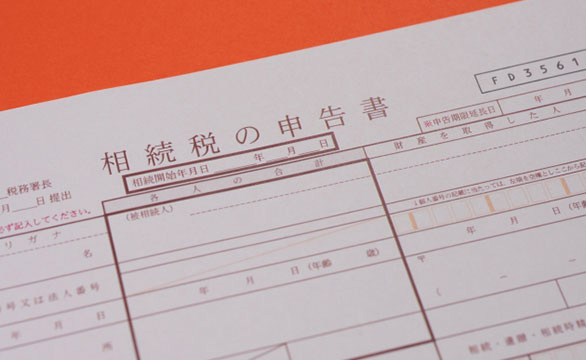
不動産相続が発生した後は、名義変更の手続き(相続登記)と相続税の申告を行う必要があります。相続登記は令和6年4月より義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を完了しなければなりません。相続人が複数名いる場合は、遺産分割協議を開いて不動産を取得する人を決め、その人物が相続登記を行うことになります。
また、相続税は、相続の発生から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。ただし、相続する不動産が住宅の場合は、不動産評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できる場合があります。
相続税の評価や計算はなじみがない上に、特例を利用できる要件も複雑です。相続に関するお悩みがある場合は、当社へご相談ください。 必要に応じて、税理士などの専門家と連携しながら、相続に関する手続きをスムーズに進めるサポートをいたします。
関連ページ:不動産の相続手続き(相続登記)の流れ
相続した不動産を放置することで生じるリスクと解決策

相続人が遠方に住んでいるなどの理由で、相続した不動産を放置すると、犯罪や火災などさまざまなトラブルの原因になるリスクがあります。
建物は管理が行き届かないと、老朽化や劣化が始まり、資産価値が低下します。それだけでなく、建物の老朽化が進むと、災害時に倒壊し、近隣の建物や人を傷つける恐れがあるのです。また、人目に付かないという点から犯罪の温床になるリスクも少なくありません。例えば、不審者に不法占拠されたり、放火など犯罪の現場になったりと、治安悪化の原因になるケースも考えられます。
さらに、空き家のまま住宅を放置すると、行政により「特定空き家」に指定されることもあります。「特定空き家」に認定されると、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍、都市計画税が最大で3倍に増加する場合があります。増税は自治体の「勧告」後、翌年の1月1日以降の課税年度から適用されるため、すぐに税額が上がるわけではありません。そのため、活用予定のない不動産は、特定空き家に指定される前に早めの売却や活用を検討することをおすすめします。
