news
【2025年最新】相続土地国庫帰属制度の問題点と解決策を徹底解説
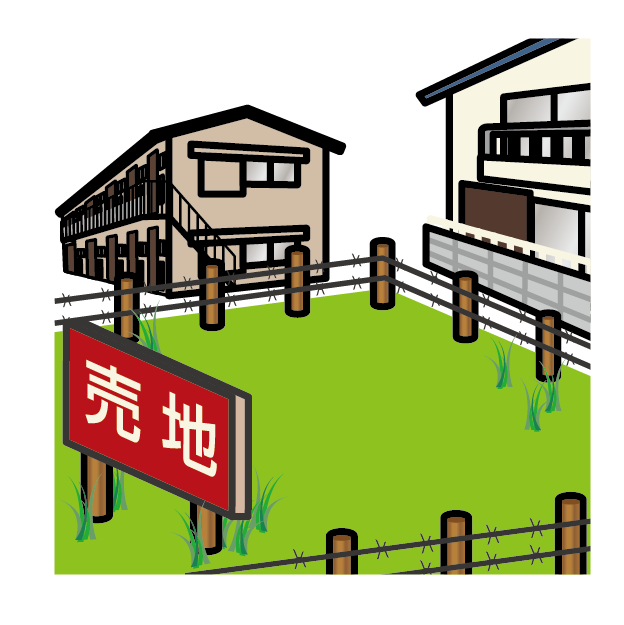
こんにちは!名古屋市瑞穂区の不動産会社「悠久ホームサービス」不動産売却サポートブログ編集部です。
相続で土地を引き継いだものの、管理に困っている方は少なくありません。特に地方の山林や農地、利用価値の低い土地を相続した場合、維持費用や管理の負担が重くのしかかります。
そんな中、2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を国に引き渡すことができる画期的な制度として注目を集めています。しかし、実際に利用してみると様々な問題点も浮き彫りになってきました。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の基本的な仕組みから現在の問題点、そして具体的な解決策まで、実務経験に基づいて詳しく解説いたします。土地相続でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
相続土地国庫帰属制度とは?基本概要の解説
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地を国庫に帰属させることができる制度です。2021年4月に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づき、2023年4月27日から運用が開始されました。
この制度が創設された背景には、所有者不明土地の増加という深刻な社会問題があります。国土交通省の調査によると、所有者不明土地の面積は九州本島を上回る約410万ヘクタールに達しており、2040年には北海道本島に匹敵する約720万ヘクタールまで拡大すると予測されています。
制度の基本的な仕組みは、相続人が法務局に申請を行い、一定の条件を満たした土地について審査を受けた後、負担金を納付することで土地の所有権を国に移転するというものです。これにより、相続人は土地の管理責任から解放され、固定資産税の負担もなくなります。
ただし、すべての土地が対象になるわけではありません。建物がある土地や担保権が設定されている土地、境界が明確でない土地などは申請できません。また、土地の管理費用を賄うため、原則として10年分の土地管理費相当額を負担金として納付する必要があります。
制度利用の条件と手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、まず申請要件を満たしている必要があります。申請できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人のみで、購入した土地や贈与を受けた土地は対象外です。
申請が却下される土地の条件は多岐にわたります。建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、通路など他人による使用が予定される土地、土壌汚染や埋設物がある土地、崖地など管理に過分な費用がかかる土地などが該当します。
手続きの流れは以下の通りです。まず、最寄りの法務局または地方法務局に承認申請書を提出します。申請手数料は土地一筆あたり14,000円です。その後、法務局による書面審査と実地調査が行われ、承認の可否が決定されます。審査期間は標準的な事案で8か月程度とされています。
承認が得られた場合、申請者は負担金を納付する必要があります。負担金の額は土地の種類や面積によって異なりますが、宅地以外の土地では20万円、市街化区域内の宅地では面積に応じて算定されます。例えば、200平方メートルの宅地の場合、約80万円の負担金が必要になります。
負担金の納付が完了すると、土地の所有権が国に移転し、相続人は土地の管理責任から解放されます。ただし、一度国庫帰属した土地を再び取得することはできませんので、慎重な判断が求められます。
現行制度の主な問題点とその背景
相続土地国庫帰属制度は画期的な制度である一方、運用開始から1年以上が経過する中で、いくつかの問題点が明らかになってきました。
最も大きな問題は、承認要件が非常に厳格であることです。法務省の統計によると、2023年度の申請件数約4,500件のうち、承認されたのはわずか200件程度で、承認率は5%未満という低い水準にとどまっています。多くの申請が却下される理由として、境界が不明確、隣接地との高低差、管理費用が過大などが挙げられています。
特に問題となっているのが、山林や農地の取り扱いです。これらの土地は相続人にとって管理が困難であることが多いにも関わらず、急傾斜地や境界不明確を理由に申請が却下されるケースが頻発しています。制度の趣旨からすると、まさにこうした土地こそ国庫帰属の対象になるべきですが、現実的には非常に厳しい状況です。
また、負担金の水準も課題の一つです。20万円という金額は決して安くなく、特に複数の土地を相続した場合や経済的に余裕のない相続人にとっては大きな負担となります。制度を利用したくても費用面で断念せざるを得ないケースも少なくありません。
手続きの複雑さと時間の長さも問題です。申請書類の作成には専門知識が必要で、多くの場合、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に依頼する必要があります。また、審査期間が8か月と長期にわたるため、その間も固定資産税の支払いや土地の管理を継続しなければなりません。
問題解決のための具体的対策と代替手段
相続土地国庫帰属制度の問題点を踏まえ、より実効性のある解決策を検討することが重要です。
まず、制度改善に向けた取り組みとして、承認要件の緩和が求められています。特に山林や農地については、一定の条件下で境界の明確化を省略したり、管理費用の基準を見直したりすることで、より多くの土地が対象となるよう制度の柔軟な運用が期待されます。
負担金についても、土地の収益性や地域の実情を考慮した算定方法の見直しが必要です。例えば、過疎地域の農地や山林については負担金を減額したり、分割納付を認めたりすることで、制度の利用促進を図ることができるでしょう。
制度を利用できない場合の代替手段として、以下のような選択肢があります。
土地の寄附は、地方自治体や公益法人、隣接地主などに土地を無償で譲渡する方法です。自治体によっては、公共性のある土地について寄附を受け付けている場合があります。ただし、維持管理費用を理由に断られることも多いのが現状です。
土地の売却も重要な選択肢です。一見価値がないように思える土地でも、隣接地主にとっては価値がある場合があります。また、太陽光発電事業者や資材置き場を探している事業者などに需要がある可能性もあります。不動産業者に相談することで、思わぬ買い手が見つかることもあります。
土地信託や一般社団法人への譲渡といった新しい手法も注目されています。専門機関が土地の管理を代行し、将来的に価値が上昇した際の売却益を分配するという仕組みです。
相続放棄は最終手段として考えられますが、土地だけでなく全ての相続財産を放棄することになるため、慎重な判断が必要です。また、相続放棄をしても管理責任が完全になくなるわけではないことも理解しておく必要があります。
制度利用を検討する際の注意点とポイント
相続土地国庫帰属制度の利用を検討する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
事前の入念な準備が成功の鍵となります。申請前に土地の現況を詳細に調査し、承認要件を満たしているかどうかを慎重に検討することが重要です。特に境界の明確化、埋設物の有無、土壌汚染の可能性などについては、専門家による調査を実施することをお勧めします。
専門家との連携も欠かせません。司法書士は申請書類の作成や法的手続きの支援を、土地家屋調査士は測量や境界確定を、不動産鑑定士は土地の価値評価を担当します。複数の専門家と連携することで、申請の成功確率を高めることができます。
費用対効果の検討も重要です。申請手数料、専門家への報酬、負担金など、制度利用にかかる総費用と、土地を保有し続けた場合の維持費用を比較検討する必要があります。特に固定資産税が安い土地の場合、制度を利用するよりも保有し続けた方が経済的である可能性もあります。
代替手段の並行検討をお勧めします。国庫帰属制度の申請と並行して、土地の売却や寄附の可能性も探ることで、より良い解決策が見つかる場合があります。また、申請が却下された場合の次の手を事前に考えておくことも重要です。
長期的な視点での判断も必要です。現在は利用価値がない土地でも、将来的にインフラ整備や開発計画により価値が上昇する可能性もあります。一方で、人口減少や過疎化が進む地域では、将来的により処分が困難になる可能性もあります。
最後に、家族・親族との十分な協議を行うことが大切です。土地には経済的価値以外にも、先祖代々受け継がれてきた歴史的・感情的価値があります。制度を利用する前に、家族や親族の理解と合意を得ることで、後のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地問題の解決に向けた重要な一歩として評価できる制度です。しかし、現在の運用状況を見ると、承認要件の厳格さや高い負担金、複雑な手続きなど、多くの課題があることも事実です。
制度を効果的に活用するためには、事前の十分な準備と専門家との連携が不可欠です。また、国庫帰属制度だけでなく、土地の売却や寄附、信託などの代替手段も含めて総合的に検討することが重要です。
今後は、制度の改善と併せて、土地利用や管理に関する新たな仕組みの構築が求められます。特に、地域の実情に応じた柔軟な運用や、負担金の軽減措置などが実現されれば、より多くの人が制度を利用できるようになるでしょう。
土地相続でお悩みの方は、一人で抱え込まず、専門家に相談しながら最適な解決策を見つけることをお勧めします。制度の理解を深め、適切な判断を行うことで、土地の負担から解放される道筋が見えてくるはずです。
監修者情報

悠久ホームサービスは名古屋市に根差した地域密着型の不動産会社です。専門知識を持つスタッフが、売買・相続・贈与・空き家活用など幅広くサポートし、お客様一人ひとりに合わせた解決策をご提供します。購入や売却の後も丁寧にフォローし、安心してお任せいただける体制を整えています。名古屋市で不動産相続や売却をお考えの際は、ぜひ当社にご相談ください。
代表取締役 山内 章寛
